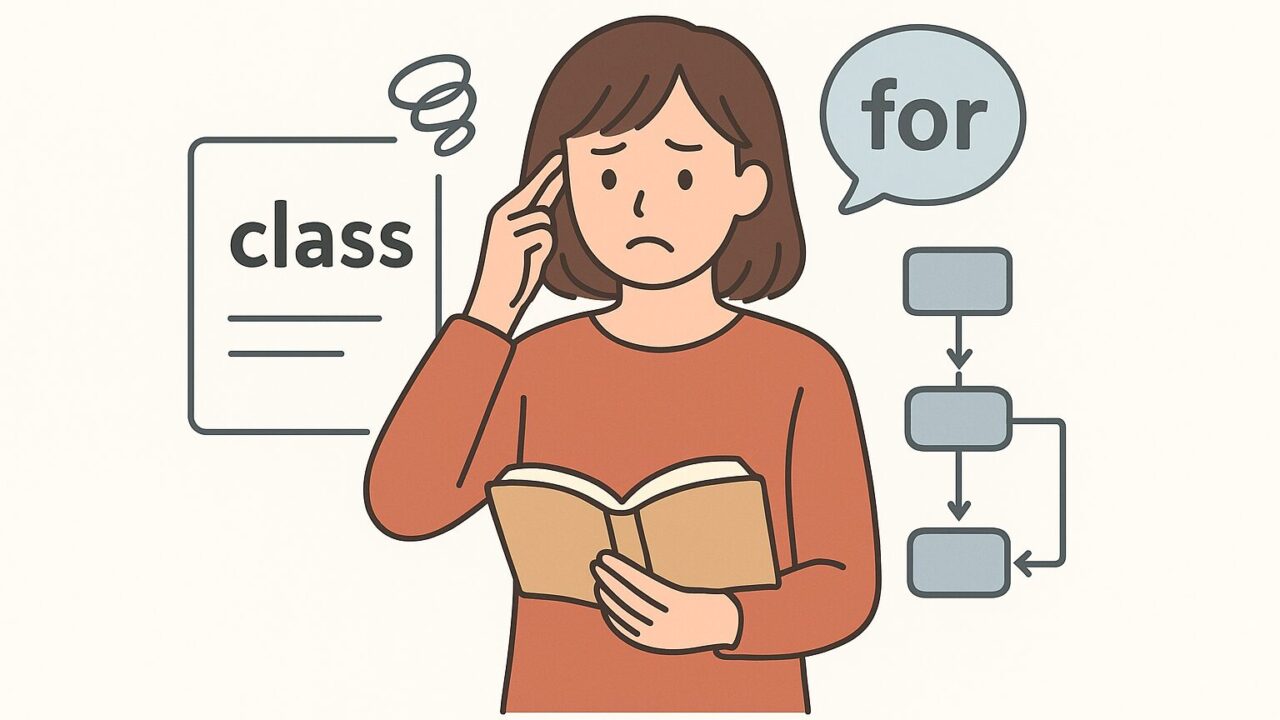プログラミング初心者が最初にやることといえば、やっぱり入門書を買うこと。私も例に漏れず、評判の良い本を次々に手に入れました。タイトルだけ並べると、もはや小さなPython図書館じゃないかとふんぞり返ってました。
「…ここまで集めれば「Pythonマスター」と呼ばれても良さそうなもんだ」と悦に入ってましたが、現実はもちろんそんな甘い話ではありません。
まずは順調:変数と型は、なんとか理解
序盤の型や変数の章は、まだついていけました。x = 5 と書けば数字が入る。y = "Hello" と書けば文字列が入る。小さな達成感を味わい、「Pythonって意外とシンプル!」と油断したのも束の間……。
強敵出現:オブジェクト指向とクラス
ページをめくると「クラス」「オブジェクト指向」という単語が登場。ここから脳内で事件が起きました。
- モニタにエラー警告 → 同時に頭の中でも「キャパオーバー!」の赤い通知が点滅。
- 説明が入ってこない → 「理解不要アラート」が脳内の
for文で無限ループ。
読んでいるだけで体内のCPU使用率100%——そんな感じでした。
動くけど、なぜ動く?サンプルコードの不思議
とはいえ、本のサンプルコードは素直に打ち込みました。するとちゃんと動くんです。
でもここでまた混乱。「動くのはわかるけど、なぜ動くのかわからない…!」
以前読んだ本に「人間はなぜ眠るのか科学的にはよくわかっていないけど、とりあえず寝る」という一節がありました。私にとってのクラスはまさにそれ。「なぜ動くのかよくわからないけど、とりあえず動く」。科学的に未解明でも人は寝る。理解できなくてもクラスは走る。
for文のネスト=突如始まる巨大迷路
次に立ちはだかったのが、for文のネスト。ループの中にループが入る、あの構造です。見た瞬間の心境は、巨大迷路に迷い込んだ観光客。
- 「ここで回って、また回って…出口どこ!?」
- 視線がコードの上をぐるぐる回り、気づけば出発点。
本を閉じたくなる衝動をなんとか抑えつつ、「これは慣れで克服する案件」と自分に言い聞かせました。
入門書あるある:説明が薄いスクリプトに出会う
入門書を数冊読み進めると、時々説明が省略されたサンプルに遭遇します。動くけど、なぜそう書くのか、どの順序で頭の中で展開すればいいのか——が分からない。
でもこれはもう、経験値の問題だと割り切りました。実務や小さな自動化で何度も書いて、「あ、そういうことか!」が積み重なるのを待つしかない。ゲームのレベル上げと同じで、「理解の筋肉」を鍛える感覚です。
今日の学び:飛ばしてOK、戻ってOK、続けてOK
- 分からない箇所は飛ばしてOK。 いずれ別の章や別の本、実務の中でつながります。
- 迷ったら戻ってOK。 「型」「変数」「関数」に一回戻ると、クラスの説明が急に理解しやすくなることも。
- まずは動かしてOK。 「とりあえず動かす→意味を足す」を何周か繰り返すのが最短ルート。
まとめ:まだ理解できないけど、いずれ分かるはず
数冊の入門書を行きつ戻りつして分かったのは、「分からないのは自分だけじゃない」という事実。そして、今は点でも、いつか必ず線になるということ。
クラスもオブジェクト指向も、for文のネストも、いつか「なるほど!」と腑に落ちる日が来るはずです。だから今日の結びはこれで。
「まだ理解できないけど、いずれわかるはず。」
明日も一歩、前へ。ゆっくりでも確実に、経験値を貯めていきます。