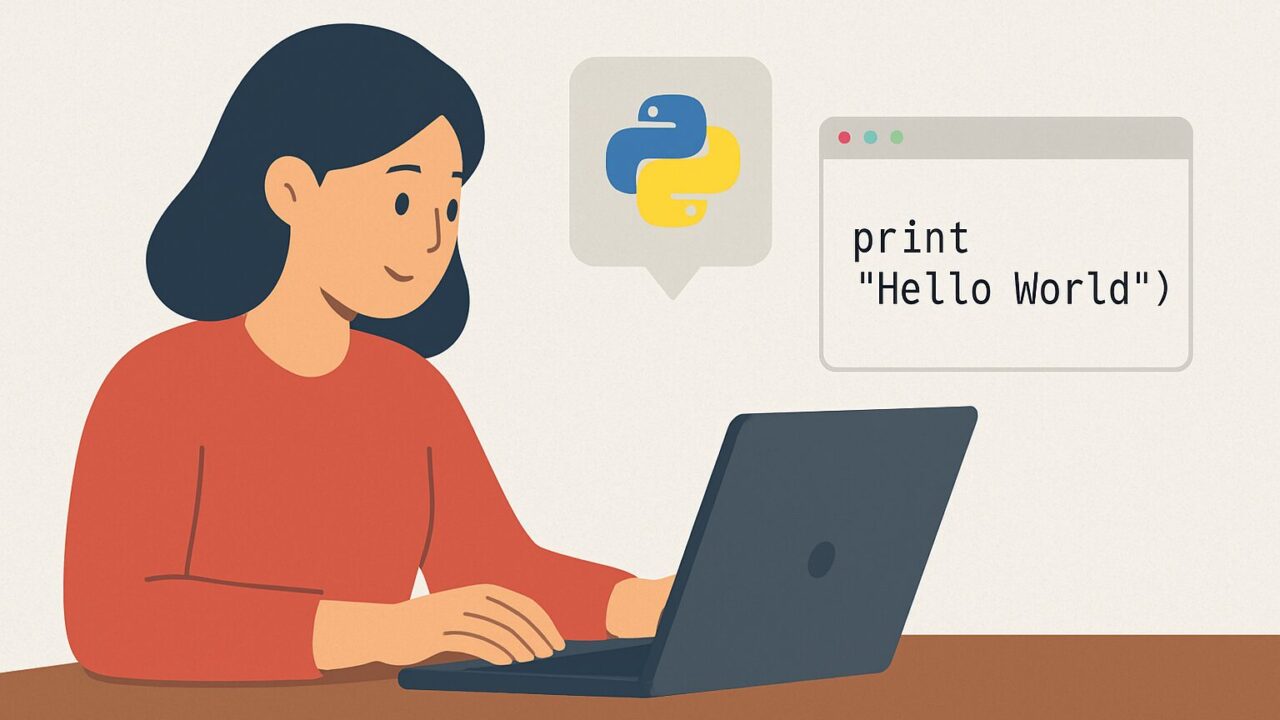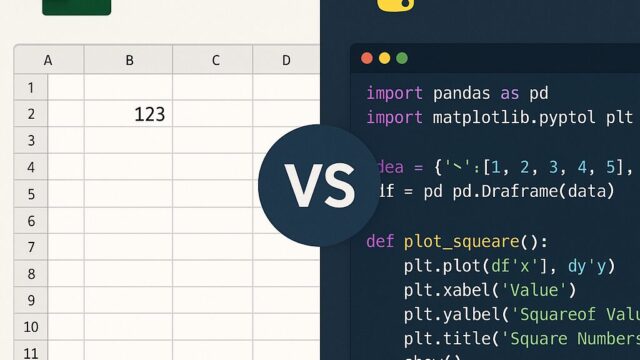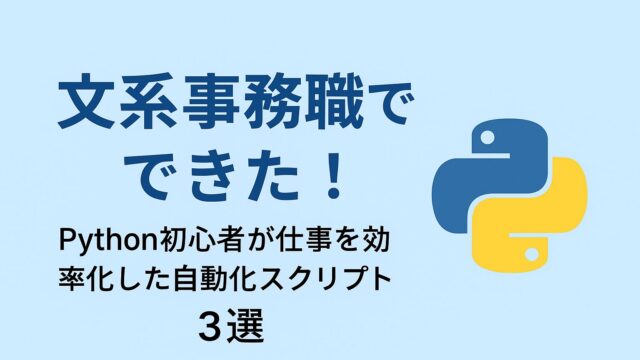このシリーズでは、完全初心者の社会人がPythonで業務効率化を目指す学習記録を、できるだけ正直に残していきます。今回は第1回、「Hello World」を動かして感じたこと、そして次の一歩について。
なぜPythonを学び始めたのか
きっかけは職場の混乱でした。前任者がプログラミングで業務を回していたものの、引き継ぎはゼロ。私が異動したタイミングでスクリプトが動かなくなり、現場は右往左往……。「このままでは再現性のない運用が続く」と危機感を覚え、一から独学で学ぶチャンスだと捉えました。
目的は明確です。業務効率化、そして趣味や知的好奇心の充足。文系・PC初心者の私でも、積み上げれば武器になると信じてスタートしました。
最初の壁:環境準備がとにかく怖い
学習環境はWindows+VSCode。参考書やサイトには「PythonとVSCodeをインストール」と書かれているけれど、初心者には「なぜそれが必要?」が分からず正直怖い。英語のダイアログや設定画面にビクビクしながら、手順を信じて進めました。
この段階で心が折れそうになる人は多いはず。でも、ここを越えると景色が変わります。「道具がそろった」だけで半歩前進です。
初めてのコード:print("Hello World")
準備が整い、いよいよ最初の一行。VSCodeで新規ファイルを作成し、拡張子を.pyにして保存。中身はたったこれだけです。
print("Hello World")
ターミナルで実行すると、黒い画面に白い文字でHello World。本当にそれだけ。でも、自分の手で書いた命令が機械を動かしたことに、思いのほかぐっと来ました。
「で、何ができるの?」という正直な気持ち
ただ同時に、「これで仕事が楽になるわけじゃないよね?」という本音も。入門書に必ず登場する儀式のような一行は、役立ち実感に直結しません。ここで離脱してしまう人の気持ち、分かります。
それでも続ける理由は明確でした。この先に“自動化”があるから。まずは「動かす感覚」を身体に入れることが大事だと、自分に言い聞かせました。
小さな達成感が恐怖心を溶かしていく
- 自分の書いた一行が画面に現れる
- 保存→実行の流れが身体に馴染む
- エラーが出ても、落ち着いて読み直せば原因に当たりがつく
たったこれだけでも、「プログラミングは自分にもできるかも」という感覚が芽生えます。最初は成果を求めすぎず、手順通りに動かす成功体験を重ねるのが近道だと感じました。
次の一歩:小さな「自動化」に挑戦する理由
目標は現実的に。いきなり巨大なツールは作りません。まずは:
- 簡単な計算(今日の売上合計を出すなど)
- テキストの整形(置換・分割・結合)
- ファイル操作(指定フォルダのファイル名を一覧化)
このあたりから始めれば、業務効率化の“手触り”が見えてきます。特に反復作業は成果が分かりやすく、モチベーションが保ちやすいです。
初心者に効いた学び方のコツ
- 一度に“全部理解”しようとしない:分からない言葉は「いったん保留」でOK。
- 手で打つ:コピペよりも、タイプして実行する体験を優先。
- 「できた」をメモ:小さな成功体験のログが、継続の燃料になります。
今回のまとめ:Hello Worldは通過点
- 環境構築は怖いけど、手順通りで半歩前進
- Hello Worldは「命令が通る」最初の成功体験
- 次は小さな自動化へ。反復作業から攻める
たった一行でも、確かに前へ進みました。ここから「ファイル操作」「テキスト整形」など、仕事で効く小さな自動化へステップアップしていきます。